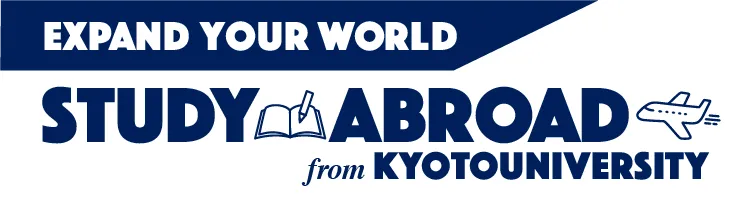先輩体験談
タイで森林再生活動について学ぶ



【名前】
中村 拓海
【学部/学年】
農学部/3年生
【参加プログラム】
交換留学
【留学先大学名】
チェンマイ大学
【留学期間】
2023年11月~2024年3月(約5か月)
温かい先生と仲間に恵まれた授業
留学先であるチェンマイ大学で所属した理学部の国際コースではタイ人学生と留学生が一緒に英語で授業を受けており、私は4科目履修しました。ほとんどタイ人の先生が担当していましたが、英語も聞き取りやすく、授業もわかりやすく熱心に教えていただきました。また、履修した4科目のうち3つは履修者が大体20人くらいで(あと一つは看護学部と合同の授業で60人くらい)、基本的に先生と学生との距離が近かったように思います。授業前後で学生と雑談することが多く、私も先生に授業について行けているか、タイ料理がちゃんと口に合っているかなど、色々と気にかけていただき、こちらからも質問や相談をしやすかったです。
しかし、学期末になるとその和気藹々とした雰囲気は一変、いくつかの授業ではプレゼンがあり、ピリッとした空気が流れます。授業前から先生は着席しており、遅刻者はもれなくチェックされ減点を食らいます。また、英語での発表のため、質疑応答ももちろん英語です。先生からの鋭い質問に即座に答えることは決して簡単なことではありません。私も発表をしましたが、やはり英語でのディスカッションでは上手く答えられていないなと感じるところもあったので、今後の研究室ゼミなどを通して練習していきたいと思っています。
一緒に授業を受けた学生は英語力が高いなと感じるとともに、フレンドリーでとてもよく話してくれる印象でした。授業初日からランチに誘ってくれたり、おすすめの場所に連れて行ってくれたりするなど、私が留学先での生活を楽しむにあたって欠かせない人たちだったと思います。
はじめは授業についていけるか不安でしたが、中間テストや期末テストさらにはプレゼンも、とにかく時間をかけて準備することで乗り切ることができました。英語力は言うまでもなく、忍耐力やタイムマネジメント力、コミュニケーション力なども少しはアップしたかなと思います。何より言語化しづらいですが、”何となく”な自信がついたのがこの留学の一番の収穫だったと思います。
キャンパスを飛び出して
課外の活動で森林再生プロジェクトにも参加しました。留学先の大学の研究ユニットが主体となって地域包括型の植林活動や啓蒙を行なっており、活動にはメンバーや大学生だけでなく、中高生や一般の人も参加しています。チェンマイは周囲を山に囲まれた街で、山地へのアクセスが簡単です。私は活動を通して、植林における考え方やノウハウを学びました。これらはおそらく今後の研究活動に大いに役立つと思います。また、個人的なチェンマイ周辺の散策や旅行を通して、タイ北部の土地利用や環境問題にも少しは触れられたように思います。
また、毎週火曜日に、チェンマイ市街で言語交換(ランゲージ・エクスチェンジ)が出来る場所があり、アジアだけでなく、欧米の人とも話すことができました。様々な国の人が集い、異なる文化や価値観を共有するとても面白い場所でした。
このように、学内にとどまらず、また英語力や教養のみならず、学外においても非常に多くのものを得ることができました。こんなに一日一日が刺激的で密度の高い時間に感じられたのも初めてで、行動の幅を広げることができたのは本当に良かったと思います。
留学を振り返って
留学の目標は、「現地の森林施業についてノウハウや考え方を学ぶこと」そして「授業等を通して英語力を上げること」でした。非英語圏への留学だったため、後者についてはさほど期待していなかったのですが、実際に5ヶ月間の生活を通して、英語を使う機会が思った以上に多く、会話力を中心として語学スキルが向上したと思います。中間テストと比較して、期末テスト対策では用語を調べる回数が減り、授業内容も入ってきやすかったです。タイというとあまり英語というイメージは湧きにくいかもしれませんが、ちゃんと英語を学ぶことができます。
今回の留学の主眼は前者でしたが、こちらも先述の通り、森林再生活動を通して、熱帯林に生息する樹種に触れ、その豊富さや重要性を実感することができました。また、日本ではあまり認知されていないバイオマス由来の土壌改良剤の存在を知り、興味が湧きました。
これから留学する人へのメッセージ
私は留学前から国際教育交流課の職員さんや学部の教務掛の方をはじめ、相談に乗ってくださった学科の先生方やASEAN拠点の先生方、そして現地で知り合った日本人留学生や学生・教職員の方々など、数え切れないくらい多くの方のサポートがあって留学ができました。また、経済的支援をしてくださった奨学金財団、何より家族の応援があったことは忘れられません。これから留学する人には、サポートしてくださる方々の存在を感じながら準備を進めてくれたらいいなと思っています。